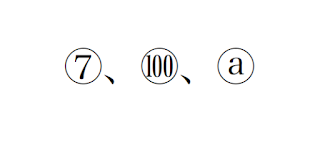tl:dr
(ここから本編)
今年の自分の仕事を軽く振り返ってみたところ、前職での最後の出版物となった『エクストリームプログラミング 』をRe:VIEWを使って制作したり、無職になってから声を書けていただいた同人サークルTechBooster の書籍制作でRe:VIEWが圧倒的に利用されていたり(年末のコミケで新刊解説書も売ってるよ! )、これまでになくRe:VIEWとの因縁めいた縁を感じる一年だった気がします。そこで、なにかRe:VIEW に関連したネタで記事が書けたらいいなあと思いました。
というわけで、TeX & LaTeX Advent Calendar 2015 のためのネタとして、Re:VIEWとTeXがもっと仲良くなれるかもしれない方法を考えてみました。TeX & LaTeX Advent Calendar 2015の昨日12月23日の担当はdoraTeXさん 、明日最終日の担当はzr_tex8rさんです。
さて、Re:VIEWの話を書くと決めたはいいものの、今年のTeX & LaTeX Advent Calendarには「今さら人に聞けない、TeXのキホン」という重点テーマが設定されています。Re:VIEWがTeXのキホンとは思えない。そこで、とりあえず形だけでも重点テーマを消化すべく、まずはTeXのキホンのひとつといえるアクティブ文字について説明することにします。TeXのキホンに興味がない人は「2. Re:VIEW風のシンタックスで書けるTeXを作ってみた 」まで読み飛ばしてかまいません。
アクティブ文字とは
TeXとかLaTeXには、俗にいうマクロとかコマンドと呼ばれるものがあるのはご存じですよね。
バックスラッシュとか円記号の後ろに英文字が並んでるやつです。
このマクロとかコマンドを使って、ページに出力する要素の構造を指定したり、繰り返し入力する手間を省いたり、特殊な記号を入力したり、装飾を施したり、絵を描いたりできるのでした。
このマクロやコマンド、ほとんどの場合は「\から始まる文字列」(専門用語ではコントロールシーケンス )という形式の名前で定義するんですが、実はもう一つ方法があって、それが本節のテーマであるアクティブ文字 です。
ようするに、単なる文字がまるでマクロやコマンドのように定義済みの内容に展開される機能がTeXにはあって、それをアクティブ文字と呼んでいます。
アクティブ文字「~」(チルダ)
アクティブ文字の代表例は「~」(チルダ)です。
ふつうのTeX環境における「~」には、HTMLにおける と同じく、ノーブレークスペースという機能が割り当てられています。
つまり、改行されるのは嫌だけどアキが欲しいような場所に「~」を挿入することで、TeXの組版処理を制御できます。
See Figure 1.1. % 「Figure」と「1」の間で改行される可能性がある
See Figure1.1. % 「Figure」と「1」の間で改行されないが、アキもない
See Figure~1.1. % 「Figure」と「1」の間で改行されず、アキも入る
この挙動が、実はTeXの実装でハードコードされている機能ではなく、次のような感じでアクティブ文字「~」として「定義」されているというわけです。
\catcode `\~ \def ~ \leavevmode \nobreak \ }
\catcodeというのが文字の種類(カテゴリコードと呼ばれています)を変更するためのTeXプリミティブで、「13」がアクティブ文字のカテゴリコードです。\catcodeで文字のカテゴリコードを13に変更すると、通常のコントロールシーケンス(バックスラッシュで始まる文字列で作れるやつ)とまったく同じ要領で、\defを使って動作を定義できます。
好きな文字をアクティブ文字に変更してみよう
もちろん、自分で好きな文字をアクティブ文字に変更して、その動作を好きなように定義することも可能です。
たとえば、「*」という文字を「\item 」に展開できると楽ができそうですよね。
\begingroup
\catcode `\* \def * \item }
\begin {itemize }
* 箇条書きが、
* こんなに、
* 書きやすく!
\end {itemize }
\endgroup
あるいは、文中の「
8」という文字をすべて雪だるまにすると楽しそうですね(
scsnowmanパッケージ マジ便利)。
She's the last of the V8s!
\begingroup
\catcode `\8 \def 8 \scsnowman [hat=true,muffler=red,arms=true]}
V8! V8!
\endgroup
問題は、こんなふうに気軽に「*」や「8」の意味を変えてしまうと、「*」や「8」という文字を本来の意味で使えなくなってしまうことです。とくに「*」は、文章中で使えないだけならまだしも(それだけでも困る場面はあるでしょうが)、\section*{連番なしの節タイトル}のような一般的なコマンドで使えなくなってしまうのは困ります。
実際、上記の2例では、\begingroupと\endgroupを使うことで、これらがアクティブ文字として有効になるスコープを制限しています。
そんなわけで、こんなに便利で楽しいアクティブ文字ですが、ふつうにTeXやLaTeXで文章を書くときに利用できるものは最初に紹介した「~」のみです。残念ですね。
(改行文字を段落の終わりとして再定義して特定の環境内で暗黙に利用しているようなケースはあります。)
アクティブ文字で、なにかもっと面白いことはできないでしょうか。
前の節では、「*」という文字を再定義して\itemのように使う方法を紹介しました。
よく考えるとこれは、Re:VIEW記法における箇条書きのシンタックスそのものです。
ひょっとしたら、アクティブ文字をさらに駆使することで、バックスラッシュと波カッコというTeXやLaTeXの記法(悪名高い)に縛られずに原稿を執筆できるところまで持っていけるのではないでしょうか。いや持っていけるに違いない。
シンプルな箇条書きの記法
長い前置きはこれくらいにして、ここからはさまざまなRe:VIEW記法をTeXで実装していくことにしましょう。
まずはRe:VIEWの箇条書き記法をTeX上で再現してみます。
新しい段落が「*」で始まったらitemize環境に入り、新しい段落が出てきたら抜けて、その間に出てくる「*」は問答無用で\itemにするが、それ以外の「*」はそのまま印字する、という動作なら、*をアクティブ文字にしてこんな感じに書けそうです。
\newif \if@itemize
\chardef \active \begingroup
\catcode `\* \active
\gdef * %
\ifvmode \@itemizetrue \begin {itemize }
\everypar ={\end {itemize }\@itemizefalse }
\fi
\itemize@to@eol }%
\endgroup
\def \itemize@to@eol \begingroup \catcode `\^^M \@@itemize@to@eol }
{\catcode `\^^M \catcode `\^^I %
\gdef \@@itemize@to@eol #1 ^^M{\review@itemize@head #1 \endgroup }}
\def \review@itemize@head \if@itemize \item \else *\fi }
TeXやLaTeXのシンタックスは捨てることにしたので、ほかのコマンドに「*」が出てくる心配はいりません。
冒頭で\catcode`\*=\activeとして実際に文書を作成してみましょう。
ただしこの実装だと、同じ行に「*」が二回出てくるとおかしなことになったり、あとに何かしら段落が存在しないと意図しない結果になったりします。
本当ならもっと作りこむべきなのでしょうが、そもそも軽量マークアップ言語なんて制作者の技術的な都合で仕様が決まるものなんだから、ここはそういう仕様ということにして先に進みます。
Re:VIEWのインラインコマンド
Re:VIEWには@<command>{content}という形式のインラインコマンドがあります。
これを同様にアクティブ文字を濫用して実装してみましょう。
\begingroup
\catcode `\@ \active
\gdef \codereview \gdef \bfreview \gdef@ <#1 >#2 {%
\def \reviewname #1 }
\ifx \codereview \reviewname \texttt {#2 }\fi
\ifx \bfreview \reviewname \textbf {#2 }\fi }
\endgroup
こちらはTeXの記法に近い(?)ので比較的安直に実装できます。
上記では等幅にするコマンド(@<code>{...})と太字にするコマンド(@<b>{...})だけを定義していますが、必要に応じて好きなものを追加してください。
章見出しや節見出し
Re:VIEWでは「=」で行を書き始めると個数に応じて階層的なヘッダになります。
これをTeXで実装しましょう。めんどくさいですが、処理自体は素直なものです。
\begingroup
\catcode `\= \active
\gdef = #1 #2 {\let \@tmpa #1 \let \@tmpb #2 %
\ifvmode \@headertrue \inc@header@cnt
\ifcat \noexpand =\noexpand #1 \inc@header@cnt \let \@tmpa \relax
\ifcat \noexpand =\noexpand #2 \inc@header@cnt \let \@tmpb \relax
\fi \fi \fi
\eq@protected \@tmpa \@tmpb }
\endgroup
\newif \if@header
\newcount \header@cnt
\def \inc@header@cnt \global \advance \header@cnt by 1}
\def \reset@header@cnt \global \header@cnt =-1}
\reset@header@cnt
\def \eq@protected \if@header \proc@header \else =\fi }
\def \proc@header %
\expandafter \gen@header \header@cnt }
\def \gen@header #1 {\@headerfalse %
\ifcase #1 \review@chapter
\or \expandafter \review@section
\or \expandafter \review@subsection
\fi \reset@header@cnt }
\def \review@chapter #1 \par {\edef \chapstring #1 }\chapter []{\chapstring }}
\def \review@section #1 \par {\edef \sectstring #1 }\section []{\sectstring }}
\def \review@subsection #1 \par {\edef \subsectstring #1 }\subsection []{\subsectstring }}
現状だとページの柱や目次に章タイトルを出力できないなどの問題は残っていますが、とりあえずできたということにします。
見出し行があるだけでずいぶんマークアップ言語っぽくなりますね。
Re:VIEWの環境
Re:VIEWでは//foo{から//}のような書式で特殊なスタイルのための環境を設定できるようになっています。
これもLaTeXの環境の記法に似ているので簡単に実現できるかなと思ったんですが、そもそもTeXには真のパターンマッチがないので、ややトリッキーな仕掛けが必要でした。
\begingroup
\catcode `\/ \active
\gdef // #1# {\begingroup \catcode `\/ \active \def // \csname review@#1 \endcsname }
\endgroup
\long \def \review@list #1 {\begin {alltt }#1 \end {alltt }\endgroup }
\long \def \review@quote #1 {\begin {quote }#1 \end {quote }\endgroup }
\long \def \review@read #1 {\begin {quote }#1 \end {quote }\endgroup }
\def \review@footnote #1 {\footnote {#1 }\endgroup }
ここでちょっと悩ましいのが、よく似た記法を持つ//footnoteのようなRe:VIEWコマンド(波カッコがない点に注意)の存在です。これにも対応するには本気でパーザを書くことになりそうなので、//footnoteコマンドでもコンテンツは波カッコで囲むということにします。
つまり、この時点でRe:VIEWとは互換性のないシンタックスになってしまっていますが、軽量マークアップ言語なんて制作者の技術的な都合で仕様が決まるものなんだから(ry
あとなんかallttの中の改行処理がうまくいってないとか、入れ子への対応が不十分とか、課題は残ってるけど深追いしない。
Re:VIEWっぽい原稿をデフォルトでロードするTeXプログラムを作る
これらの定義をプリアンブルに書いたりスタイルファイルに書いたりして、LaTeXの \begin{document} ... \end{document} の間で実行するだけでも面白いといえば面白いのですが、どうせなら、.reファイルから直接PDFを組版できる独立したコマンドがあると便利ですよね。
というわけで、上記のマクロたちをフォーマットとしてまとめておきました。
revtex: TeX with Re:VIEW syntaxhttps://github.com/k16shikano/revtex
いちおう補足しておくと、TeXの文脈でフォーマットといったら、initexを使ってダンプする(あるいはダンプした)ファイルのことです。
そのフォーマットをデフォルトで利用するrevtexという新しいTeXの実行ファイルを作ることで、Re:VIEWっぽい記法の原稿を直接コンパイルできるようにしようというわけです。
日本語を組版したいので、ベースにするのはuplatexコマンドとします。
uplatexの実行ファイルをrevtexという別名で用意し、上記のフォーマットをかませて使うように設定すれば、こんなふうにTeXで直接、ほぼRe:VIEW記法の原稿をコンパイルできるようになります。
$ ls -la /usr/bin/revtex # revtexはuplatexのシンボリックリンク
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Dec 22 12:28 /usr/bin/revtex -> /usr/bin/uplatex
$ cat sample.re # sample.reは(ほぼ)Re:VEIW記法のファイル
= はじめてのUNIX
== 実際すごい
重金属を含んだ酸性雨が降りしきるなかをものともせず、
@<b>{マグロツェッペリン}//footnote{巨大飛行船}が回遊する!
* ネオサイタマ
* マルノウチ・スゴイタカイビル
その頂から退廃的な高密度ネオン看板が瞬く地獄めいた都市の喧噪を見下ろす影がひとつ急降下した。コワイ!
== もっとすごい
「こんにちはニンジャ・スレイヤー=サン。」
そういって敵は姿を見せぬまま@<code>{UNIX}端末にログインした。
= インガオホー
こんにちはダークニンジャ=サン。ハイクを詠め!
//quote{
トチノキ、フユコ……
}
#@# fin
$ revtex sample.re # ほぼRe:VIEWな原稿がTeXでコンパイルされる
This is e-upTeX, Version 3.14159265-p3.6-u1.20-141210-2.6 (utf8.uptex) (TeX Live 2015/Debian) (preloaded format=revtex)
restricted \write18 enabled.
kpathsea: Running mktexfmt revtex.fmt
...
いうまでもありませんがRubyもRe:VIEWも不要です。最後にdvipdfmxが何か言ってますが、無視する方向で。
生成されたPDFを以下に張っておきます。
画期的ですね。
実は、少なくともひとつ、どうにも解決できないダサい制限があって、原稿ファイルの末尾にオリジナルのRe:VIEWではコメントとして無視される「#@# fin」という行を書いておく必要があります。
TeXは組版をするとき、\endというプリミティブで原稿ファイルの終端に到達したことを知るのですが、Re:VIEWにはそのための記法がないので、こうしてお茶を濁しているわけです。
(追記)
と思い込んでいたら、e拡張には\everyeofなるそのまんまなプリミティブがあると教えてもらいました。
これを使うと、確かに最後の行が不要になるので、ひそかにあきらめていた行コメントも実現できました。(追記おわり)
免責と今後の展望
auxによる参照解決とか、エスケープとか、いろいろさぼってるので実用品ではありません。
また、これ以上Re:VIEW対応率をあげようとか、バグを直そうとか、そういう予定もたぶんありません。
むしろ、あらためてMarkdownっぽいのを実装するほうが面白そうかも。
参考資料
TeX by Topic
TeX芸には欠かせない説明不要の名著。日本語訳もあるが入手は困難。原著者のサイトで英文なら全部読める。
1TeXの実装 TeX芸の北極。文字「1」をアクティブ文字にすることで、文字通り「1」のみでTeXコンパイル可能な文書を作る。
xmltexの実装
XML文書をTeXでコンパイルするという、海外のTeX芸のひとつ。
Re:VIEWフォーマットのドキュメント これ以外にもいろいろ隠しコマンドがあるらしい。